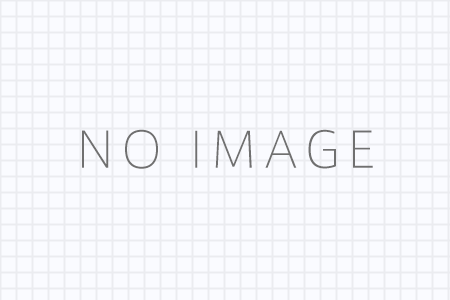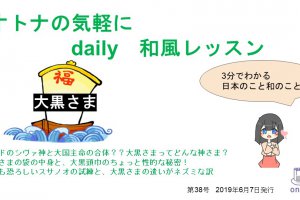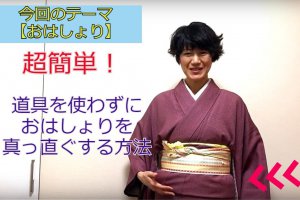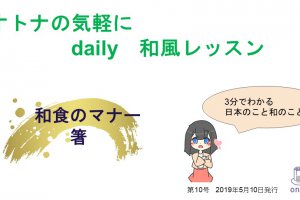Contents
二十四節気【白露】~重陽の節句の新しい習慣・後の雛~

本日は二十四節気の【白露(はくろ)】です。

聞いたことがありません・・・

二十四節気とは
二十四節気とは、一般的に用いられる四季、春夏秋冬をさらに細かく、
それぞれ6つの季節に分けたもので、太陽の動きを元に定めたものです。
365÷24=15.20… おおよそ15日毎の季節を表した言い方で、月に2回ずつあります。
平安時代に広まり、日本古来のものと思われていますが、
実は発祥元は中国となります。
ですので、日本の暦と若干のズレを感じることもありますが、
農業の目安として日本にも取り入れられ、活用されてきました。
| 春 | 1.立春 | 2.雨水 | 3.啓蟄 | 4.春分 | 5.清明 | 6.穀雨 |
| 夏 | 7.立夏 | 8.小満 | 9.芒種 | 10.夏至 | 11.小暑 | 12.大暑 |
| 秋 | 13.立秋 | 14.処暑 | 15.白露 | 16.秋分 | 17.寒露 | 18.霜降 |
| 冬 | 19.立冬 | 20.小雪 | 21.大雪 | 22.冬至 | 23.小寒 | 24.大寒 |
わたしたちは、日々、ざっくりと、春夏秋冬の四季くらいは
感じながら生きていますが、
二十四節気だと、それが月に2回巡って来る訳です。
季節を感じる心と感覚が育ちますし、
今どんな花や鳥や虫が活動していて
どのような時期なのかを知ることは、
旬のものや、季節をより多く実感でき、
暮らしが、心が豊かになっていきます。
ほら、旬のものを食べると嬉しくなるし、
元気になりますよねぇ。
旬のものには、地球のエネルギーがいっぱい詰まっているからです(*^^*)

栄養が含まれていますものね!
からだに取り入れる栄養面だけではなくて、
エネルギーという観点からみても
生きることに満ち満ちているので、
意識して取り入れていきたいですね♪
【白露】の時期は、様々な行事がある期間
9月8日は白露(はくろ)です。朝晩の気温が下がり、
地面に近い空気中の水蒸気が露となって葉や花につく頃です。
頃というのは、二十四節気は、太陽の動きを元にした角度が成り立つ
その日のみを言う場合もありますし、
恐らく、広く使われている方は、
期間の方で、当日から次節気の前日までのことを言います。
二十四節気【白露】についての
daily和風レッスンはこちら!
3分で今まで目を向けてこなかったものに対しての
大切さや、由来、文化、マナーなどを
簡単にチェックできます(*^^*)
(注)動画ですので音が出ます
2019年の白露の期間は、9月8日~9月22日までとなります。
立春とか、夏至、秋分みたいに有名なものではないのですが、
次節気の秋分を迎えるまでに、実に様々な行事があります。
9月9日は重陽(ちょうよう)の節句、
9月11日は雑節の二百二十日
(立春から数えて220日目で風に注意する日で農家の三大厄日と言われている)
9月13日は十五夜(中秋の名月)
9月16日は敬老の日
9月20日は彼岸入り
9月23日は秋分の日で、昼と夜の長さがピッタリ同じになる日であり、
お彼岸の中日でもあります。
(正確に言うと、秋分は次節気です)
どれも秋を感じさせる行事で、
知っていても、すぐに忘れてしまう十五夜など、
意識して、月を眺める時間をとってみるのも
良いかもしれません。
なかなか普段の生活が慌ただしくて、
美しいものを見て心を休める時間って
確保できないですが、
そういうことを大切に出来るのが、
素敵なオトナだなって思います(*^^*)
是非一緒に目指しましょう♪
9月9日の重陽の節句、広めていきたい後の雛

動画の中でも触れていますが、
9月9日、重陽(ちょうよう)の節句は、
桃の節句や端午の節句と並ぶ五大節句のひとつで、
【菊の花に綿を被せておき、朝露を含んだ綿で身を清める】
という習わしがありました。
だいたい、日本に古くからある風習や、習慣には、
こした【身を清める】ことを目的としたものが多いです。
驚くほど多いんですよ。
で、こちらの節句も実は中国由来(笑)
輸入したものが変化を遂げて
今の日本独特のカタチになっています。
二十四節気もそうですが、
昔はかなり大陸の影響を受け、
取り入れているのがわかりますね。
しかし、新暦になってからの暦のズレで、
菊の花自体があまり咲いておらず、
残念ながらマイナーになってしまっている節句です。
(実際菊祭りなどと呼ばれる祭りは、
10月に行われることが多いですよね。)
反面、見直されているところもあり、
桃の節句から半年後の、【オトナのひな祭り=後の雛】として、
仕舞ってあったひな人形を菊の花と共に飾る
という風習が出来つつあるようですね!
実用的な面では、虫干しにもなりますし、
やはり、年に1度だけ飾るというのも
せっかく持っているのに勿体ない気がしますよね。
お雛様は何歳になっても女性の心を捉えるものです。
良いなと思ったら、飾るスペースを確保して、
是非真似してみてください。
【重陽の節句=菊の節句】の楽しみ方

それでは、ここで重陽の節句の楽しみ方をお伝えしますね♪
まずは、菊酒。
食用の菊の花は、スーパーでも手に入ります。
200~300円くらいですね。
このなかの花びらをお酒に浮かべて飲んでみる。
味はしないですが、気分を味わうことが出来ます。
そういえば、お祝いの席で出される【桜湯】も
桜の花を塩漬けにしたものにお湯を注いで作れるものですから、

花を愛でながら、飲み物をいただくというのは、
日本人が昔から行ってきたことなんでしょう。
盃や湯呑に浮かべるのを
花を眺めながらお酒を飲むに変化したものが、
みんなが大好き【花見】とも言えますね。
この菊と桜は、一般的に日本の国花と言われており、
春と秋を代表する花でもありますね。
菊の花というと、どうしても、仏花のイメージがつきますが、
○○マムという名前の小振りなものも菊の一種で
大変可愛らしいですし、
菊花紋章は、家紋としても多く使われていますし、
天皇や皇室を表すのは、八重菊をさらに重ねた十六葉八重表菊ですね。
和菓子

菊をモチーフにした干菓子や菊饅頭もありますが、
着せ綿といって、お花にふわふわの綿が乗っている
和菓子があります。
こちらの方が気軽かもしれませんね。
和菓子は多くいただくものではなく、
少量を楽しみながらいただくものなので、
そうした食べ方をすることで、
心に余裕がでてきそうですね(*^^*)
飾る
 また、前半でもご紹介しましたが、
また、前半でもご紹介しましたが、
この機会にお雛様がある家庭は、
飾ってみてはいかがでしょう??
自然の中に季節を感じることはもちろん、
そうした空間を自ら作り出すというのも
また、楽しい時間となりますよ!
まとめ
暑さにぐったりとしていた夏も終わり、
本当に過ごしやすくなってきました。
二十四節気という月に2回訪れる
季節を肌で感じることができるようになると、
心に余裕が生まれてきますね。
古くからの風習を知り、
現代風にアレンジした後の雛も素敵な習慣だと思いませんか?
是非、ご自身ができるところから始めて、
感受性を豊かにしていきましょう。
それでは、本日も最後までお読みいただき、
誠にありがとうございました!

「日本人で本当に良かった!」と心から感じる時間が増えることを応援してます!
【お知らせ】
着る活動で和服を22世紀に繋いでいくきもの講師が、
【草木染めワークショップ】を開催することになりました!